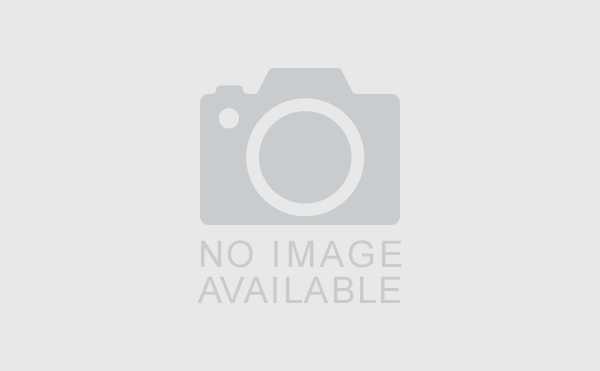小坂まさ代2024年第4回定例会一般質問~2.孤独・孤立対策について
2孤独・孤立対策について
○小坂
令和6年4月1日に孤独・孤立対策推進法が施行された。自治体においては地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォームをつくり、保健、医療、福祉等の専門機関及び専門職、社会福祉法人、社会福祉協議会、学校及び教育関係者、NPO、住民組織、民生委員や児童委員、ソーシャルワーカー、社会支援コーディネーター、ボランティア等との連携が求められているが、本市では重層的支援体制の中で取り組んでいると認識している。法律が施行となった現在の状況について伺う。
○健康部長
本市においては、第2次地域福祉計画を令和6年3月に策定。当該計画には重層的支援体制整備事業実施計画を包含し、施策の一つに事業としても位置づけている。第2次地域福祉計画を検討する過程では、同計画の策定検討委員会で委員より意見をいただき、国の孤独・孤立対策を踏まえ、策定をした経緯がある。孤独・孤立という課題に対しては、様々な相談支援機関の連携が重要であり、本市では、全国的にも先進的に取り組んでいる重層的支援体制整備事業における多機関協働事業により、個別ケースの支援に当たっている。孤独・孤立は、その課題を抱える方にとって複合化した生活課題のうちの一つであることもまれではなく、また、課題の特性上、支援につながりにくいと考えられる。現在、重層的支援体制整備事業では、各相談支援機関が捉えた様々なケースを、関係する各種の機関が参加する支援会議において共有・連携し、支援に向けて、アウトリーチによるアプローチを含めて検討することを行ってきている。
○小坂
孤独・孤立対策において、若年層からの支援が必要であると考える。本市での今年度の若者支援の取組について伺う。
○子ども家庭部長
今年度の事業展開としては、ひきこもり等になって長期化する状態を少しでも早い時期に予防するような効果が期待できないかという視点から、15歳から18歳頃の時期に、生きづらさや社会生活を営む上での困難を抱え込んでしまう前、どんな状況があったらその先に進まずに済むかを検討している。当事者と同じような年代の国分寺高校や早稲田実業の高校生に協力をいただき、また、ひきこもり等の当事者会にも、「ひきこもり等になる前にどのような場所があったら苦しまなくて済みそうだったか」というようなお話を伺った。今後、いただいた意見をネットワーク会議の各支援機関の支援者で共有し、どのような形がよいかも含め、マップや居場所についてまとめる検討を進めていく予定。
○小坂
現在、市で行っている居場所づくり懇談会についても伺う。
○子ども家庭部長
子どもの居場所について活動している団体、関係者が相互の取組に関する情報交換や連携のきっかけとなり得るネットワークづくりを行う場として、子どもの居場所づくり関係者懇談会を年3回実施しており、今年度2回目を先日開催した。22人が参加。それぞれの場所で関わっている子どもたちはどのような子どもたちか、関わる難しさや課題と感じていることは何か、今、関われてはいないが、市内にこういった子どもたちがいるのではないかというようなことをグループワークして、意見の発表をしていただいた。どのグループの発表からも、小学校低学年の子も徒歩で行ける場所で、安全・安心な運営をしていただいている様子が分かった。
○小坂
つながりをつくる上でも、情報共有する場としても重要な取組であると考える。ここで聞かれた声を、ぜひ施策に生かしていっていただきたい。居場所となるための条件とは、物理的な空間だけではなく、人間関係なども含むもの、一人一人にとって主観的なもの、そこに行きたい、いたい、と思え、誰かといてもいいし、1人でいてもよく、何かをしてもいいし、何もしなくてもいいという遊びや余白が必要なもの。居場所とは、誰かに決めてもらうものではなく、一人一人が「ここが自分の居場所だ」と感じられる必要がある。ゆえに数多くの場所が必要。居場所をつくりたいと思っている、また既につくっている市民や団体の後押しをしていただきたい。国や東京都も、子どもの居場所づくりに多くの予算をつけている。ぜひ活用の検討を。