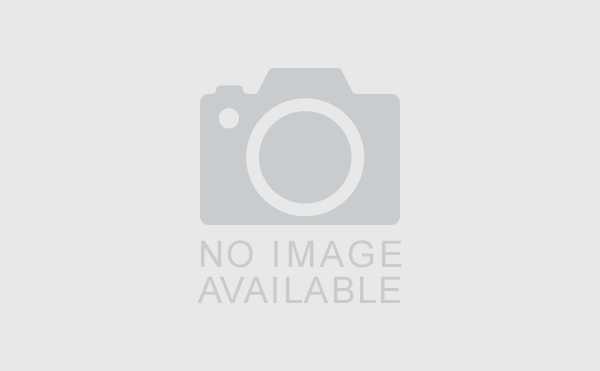小坂まさ代2024年第4回定例会一般質問~1.すべての子どもを大切にした教育を①
1.すべての子どもを大切にした教育を
○小坂
今年度は第2次教育ビジョンの最終年度となる。施策の方向性1では「生きる力の育成」を掲げ、その4「一人ひとりの個性を伸ばします」とあるが、大変残念ながら学校に通えない子どもが増え続けており、また、通えていても個別最適な学びや合理的配慮を受けられず、困難さを抱えている子どもたちがいる現状がある。今回は市として、そうした子どもたちに対してどのような対応をしているのかを問う。
(1)外国にルーツのある子どもの支援
令和元年、日本語教育の推進に関する法律が施行となり、地方公共団体は地域の状況に応じた日本語教育推進施策を策定、実施することとなった。基本理念において、「外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会の最大限の確保」とある。文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」の結果を見ると、公立学校における日本語指導が必要な児童・生徒は令和3年度5万8,307人、うち外国籍4万7,619人、日本国籍1万688人、令和5年度は6万9,123人、うち外国籍5万7,718人、日本国籍1万1,405人となっており、僅か2年で1万人以上も増えている。まず、本市における外国人人口が増える中で、外国にルーツのある子どもも増えていると認識しているが現状について伺う。
○市民生活部長
市内外国人人口については、年々増加しており、令和6年度は3,203人。特に昨年度から今年度にかけて増えている。なお、3,203人のうち6歳から11歳が136人、12歳から14歳は36人。近年特に増加している国籍は中国、ネパール、ベトナムなど。
○小坂
令和元年第4回定例会で会派の議員が請求した資料によれば、令和元年11月1日の本市の全外国人人口は2,566人、うち6歳から11歳は66人、12歳から14歳は28人となっていた。この5年で小学生に当たる子どもは約2倍、中学生に当たる子どもは約3割増。
日常会話ができても、学習に必要な読み書き能力がついていない子どもは授業についていくことができない。学習に支障がないよう、日本語支援が必要な児童・生徒には別室に取り出して支援をしている。今年度は市内15校のうち約半数の7校で14人の子どもが日本語の支援を受けているとのこと。まず、この日本語指導員派遣の仕組みについて説明を。
○教育長
日本語指導員の派遣事業は、外国人児童・生徒等が学校において日常生活及び学習活動を営む上で必要な基礎的な日本語の指導を実施するもの。外国人児童・生徒が入学や転学等をした場合には、まず、担任等が学級での生活や学習の様子を把握、保護者からの聞き取りも含めて、学校においてどのような支援ができるか検討を進める。その上で学校が教育委員会に日本語指導員の派遣を申請し、指導主事が対象児童・生徒の状況を観察した上で派遣の決定をしている。日本語指導員は、登録された方の中から当該児童・生徒の言語等に配慮しながら状況に応じて派遣を行っている。指導に当たっては、別室で日本語指導を行ったり、教室の授業で対象児童・生徒のそばについて学習内容の意味を説明したりするなど、実態に応じて支援している。
○小坂
今年3月、東京都では多文化共生社会に向け、ともに学び成長する児童・生徒の育成を目指して、日本語指導推進ガイドラインを策定。これによれば、日本語指導が必要な児童・生徒は、令和4年度の東京都の調査では都内公立学校に4,377人在籍、うち外国籍の児童・生徒が約3,400人、日本国籍の児童・生徒が約900人であるとされている。外国人児童・生徒等が共生社会の一員として学校生活を送ったり、教科等の授業を理解したりする上で必要な日本語の能力や学力と、社会で生きていくために必要な力を身につけられるよう、一人一人の実態に応じた指導支援を推進するとある。児童・生徒の中には、日常的な会話に支障がないため支援の必要性が見過ごされている場合があるのではないか。日常会話の力、生活言語能力と学習で求められる力、学習言語能力は異なる。生活言語能力はある程度は日常生活の中で身につくと言われているが、学習言語能力は生活の中で身につきにくく、日本語指導担当教員が必要となり、学校での計画的な支援が必要。このガイドラインがどのように共有され、徹底されているか、学校では実際にどのような工夫がされているか伺う。ガイドラインで作成が推奨されている個別指導計画が策定されているかどうかも確認したい。
○教育長
このガイドラインについては、本年4月に東京都教育委員会から通知があり各学校に周知し共有した。各学校では本ガイドライン等を参考にしながら、学校生活に不安がないように担任等が丁寧に状況を把握し、必要に応じて日本語指導につなげるなど、安心して生活できるように支援している。
ガイドラインで示されている個別指導計画だが、これは特別の教育課程を編成する際に必要となっている。法令によれば、特別の教育課程の指導者や個別指導計画の作成者は教員免許を有する教員となっており、その教員は1校に一定数の外国人児童・生徒等が在籍する場合に申請できるということになっている。本市の学校ではこの条件から外れていることから特別の教育課程を編成しておらず、また個別の指導計画を作成していない状況。ただ、日本語指導員と担任が日々の指導内容や、また学習の状況など細かく共有しながら丁寧に対応している。
○小坂
東京都では今年度より地域日本語教育コーディネーターを配置した。市区町村で配置しているところもある。こちらは今後の研究を求めておきたい。日本語指導員派遣は本市の場合、108時間を上限としている。さらなる支援が必要とされる場合もあるのではないか。どのような支援があるのか。
○市民生活部長
日本語指導員派遣による対象児童・生徒の理解度等を勘案し、各学校より引き続きの支援を要請された場合については、人権平和課で実施している「日本語支援サポーター派遣事業」を活用して支援している。こちらも108時間を上限として、国際協会を通じて日本語支援サポーターを対象児童・生徒の学校へ派遣し、放課後等において学習支援を行っている。
○小坂
今月から始まった外国籍等の児童・生徒の日本語支援サポーター養成講座に参加しているが、ボランティアを希望されている方は多数いらっしゃり、熱心に学ぶ姿が見られる。現在、上限が108時間とのことだが、必要な子どもにはさらなる追加の支援も検討を。令和5年度サポーター派遣実績は僅か5名。こうしたボランティアによる支援があるということがあまり知られていないのではないか。学校の教員や保護者への周知について伺う。
○市民生活部長
支援が必要な子どもにしっかりとサポート事業が行き届くよう、周知は重要と認識。これまでも各学校等への日本語指導員派遣、日本語支援サポーター制度の説明、周知をしているが、対象児童・生徒の担任の先生や保護者に対しても周知と理解を求め、掘り起こしができるよう、今年度は制度案内等をまとめたリーフレット作成を行っているところ。作成に当たっては学校指導課、国際協会、また、こいがくぼ国際教室を主催している恋ヶ窪公民館等をメンバーとした地域日本語教育在り方検討委員会を開催して進めている。
○小坂
活用や周知を進め、支援を必要としている子どもたちが取りこぼされないよう学校と連携し、寄り添った支援を求める。さて、日本の学校において、いじめを経験する外国ルーツの子どもは少なくない。学校における異文化理解や多文化共生の考えが根づくような取組について伺う。
○教育長
各学校においては、児童・生徒が異文化を理解し、尊重する態度の育成に向けて様々な取組を行っている。特に小学校からの外国語教育や総合的な学習の時間など、国際社会や異文化への理解につながる学習を進めている。ある小学校では、オーストラリアの小学校とオンラインで交流し、七五三や漢字などの日本文化を紹介し、相手先の小学校からは歌の紹介をしてもらった。今まで学習した英語を使って質問するなど交流をさらに深め、異なる文化と接するよい機会となった。このように各学校において様々な創意工夫をしながら、異文化理解が進むように取り組んでいきたい。
○小坂
多文化共生社会を目指す上で、国分寺市でも外国人人口が増加している現状を踏まえ、まずは外国人市民の実態やニーズを把握する必要があるのではないか。アンケートやヒアリングの実施についての検討を求める。