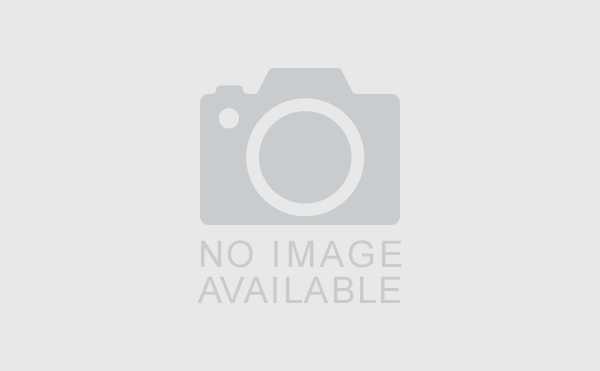小坂まさ代2024年第4回定例会一般質問~1.すべての子どもを大切にした教育を③
(3)学校に行けない子どもの支援
○小坂
先月末に文部科学省より、令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等児童・生徒指導上の諸課題に関する調査結果が公表された。小・中学校における長期欠席者数は前年度から約3万3,000人増の49万3,440人、長期欠席のうち不登校児童・生徒数は前年度から15.9%増の34万6,482人と11年連続増加し、増加率は前年度と比較して若干低くなったものの、その数は過去最多。低学年から通えなくなってしまう児童が増えており、対応が求められている。フリースクール等に通い、東京都の調査に協力された方は増えているものの、全体の1割程度である。学校に通えないことで学習できないだけではなく、人との関わりや体験の欠如、体力や自己肯定感の低下など、成長に必要な多くのものが失われており、しっかりとした支援が必要。
八王子市教育委員会では、学校、保護者、関係機関が十分な連携を図り、不登校児童・生徒の社会的自立に向けた努力を積極的に認めていくという方針を打ち出し、本年6月、市立学校共通のガイドラインを策定した。その中にはこう書かれている。「不登校をめぐる課題は、現在の学校教育が抱えている最も重大で喫緊の課題であるとともに、児童・生徒一人一人の教育の機会をいかに確保するか、また学校の役割とは何かという問いを私たちに投げかけているものであると考えます。今般、学校に登校できない児童・生徒が、学校外で取り組んでいる懸命な学びに向けた努力を可視化し、適切に評価していくことで、不登校児童・生徒の出席を認めていくための考え方について『八王子市立学校における不登校児童・生徒の出席と取扱いに関するガイドライン』として整理しました」
現在、本市では、学校外の学びや放課後の登校についての出席の扱いや学習評価については、各学校長の判断となっている。学校によって差が出ないよう、どの学校に通っている子どもに対しても国分寺市として平等に出席扱いや学習評価がされるようガイドラインを作成していただきたい。出席数や評価は内申点に大きく影響し、進学先だけではなく、その後の人生に関わる。教育長の見解を伺う。
○教育長
不登校の課題については、本市においても最重点で取り組まなくてはいけない課題であると認識している。出席の取扱いや学校外の学びの評価については、国の通知に基づき適正に平等に行っている。令和6年8月29日の文部科学省通知「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」には、学校に通うことができなくても、民間団体等の学校外の機関や自宅等で学習を続けている不登校児童・生徒の努力を評価し、学習の成果を成績に反映できることが法令に位置づけられたことが示されている。また、令和元年10月25日の文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」に出席扱いの条件について示されている。本市においては、これらの通知の内容を校長会で改めて確認している。個々の児童・生徒の状況に応じて適切な対応が求められているので、各学校の事例について共有し、研究を行っているところ。いずれにせよ、この通知の趣旨に従い、適切に出欠の取扱いを行うとともに、可能な限り不登校児童・生徒のあらゆる努力を肯定的に評価するよう取り組んできた。また、これからもそのような姿勢で取り組んでいく。なお、八王子市のガイドラインについては、出席の取扱いに係るものだと認識をしている。このガイドラインにおいても、本市と同様、校長の確認と判断という下で評価が行われていると、評価の出席の扱いが確認されているということが明記されているので、私どもと同様であろうと思う。特に、八王子市は大規模な地区であるので、全ての学校で共通に理解するためには、こういうガイドラインも必要不可欠であろうと思うが、その内容や活用方法については、まず勉強させていただきたい。○小坂
文科省の通知どおり、本市においても全ての学校で同様に出席扱いや評価がされるということを確認をした。続いて、サポート教室と今年度拡充された別室登校支援について伺う。拡充されたことにより見られた変化について。また、不登校児童・生徒が増え続けている現状を鑑み、来年度以降もさらなる充実を強く要望しておきたい。見解を併せて伺う。
○教育長
サポート教室は学習の補充に向けて開設され、不登校児童・生徒への対応も行っている。開室時間や曜日が増えたことにより、児童・生徒がサポート教室に通いやすくなったという報告を受けている。日によって心身の状況が変わる不登校児童・生徒が本人の状況に合わせてサポート教室に通うことができることで、サポート教室への登校が習慣化され、好転傾向が見られるようになったと聞いている。今後もサポート教室も含めて、不登校に係る様々な取組を充実させていきたい。
○小坂
サポート教室は、登校はできているものの、学習面での遅れが見られるなど、心配な子どもに対してもサポートする役割を担っているが、学校によっては、放課後に配置する支援員の予算がない現状があると聞いた。不登校の子どもへのアンケートによれば、学業の不振は不登校の大きな要因の一つ。新規の不登校児童・生徒を生まないためにも、また午前中の活動が困難な起立性障害の子どものためにも、放課後の支援員の配置が必要だと考える。こちらについては、来年度、予算委員会の際に改めて確認をさせていただきたい。
続いて、今年度より始まった不登校巡回指導員について伺う。
○教育長
不登校巡回教員については、市内中学校を巡回し、不登校生徒への直接的な支援や不登校生徒の支援の助言などを行っており、校内における組織的な支援体制の整備について幅広く支援し、不登校の未然防止や不登校生徒への支援の充実を図るといったことを目的としている
○小坂9月に開催された不登校担当者連絡協議会について参加者や内容など報告を。○教育長
不登校担当者連絡協議会については、各校の不登校担当者を対象に開催をし60名ほどが参加。各校の生活指導主任や養護教諭、サポート教室支援員、スクールカウンセラーやスクール・ソーシャルワーカー、トライルーム指導員や教育相談室の相談員が参加し、不登校総合対策としてまとめた「つなぐプラン」を共有するとともに、本市の不登校児童・生徒の状況やサポート教室の取組事例について情報共有をしたり、各担当における支援の在り方などを協議したりすることで、各学校における不登校対応力の向上につながったのかなと考えている。
○小坂
今回初めての取組で、今年度は1回のみの開催とのこと。ぜひ今後も進めていただきたい。不登校児童・生徒の数を考えると、年に1度では不十分なのではないか。来年は拡充を。
さて、教育委員会では、「お子様の学びや生活について、不安やお困り事ありませんか?」というリーフレットを作成し、「1人で悩まず、一緒に子どもの社会的自立に向けて取り組んでいきましょう」と呼びかけている。こちらのリーフレットの作成に当たって、また作成後の庁内連携について伺う。
○教育長
市長部局の関係課と連携をし、目的を共有した上で必要な情報を集約し作成した。また、本リーフレットは、長期休業日前の7月に、全ての児童・生徒及びその保護者を対象として配布をした。今後は、各担当でリーフレットを活用しながら、相談支援を行っていくとともに、関係各課とも連携をし、情報に変更があった場合には、適宜修正を行って、一層の周知を図っていきたいと考える。
○小坂
子どもが学校に通えなくなったことで離職を余儀なくされ、精神的な不調を抱えている保護者の方も多くいる。教育部と福祉部、子ども家庭部など、さらなる深い連携による子ども支援、親支援を。本年8月の文科省の通知によれば、「学校教育を受ける機会、周囲の児童・生徒と交流や切磋琢磨をする機会を得られないことにより、当該児童・生徒が将来にわたって社会的自立を目指す上でリスクが存在することを踏まえ、児童・生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち、児童・生徒が不登校にならない、誰もが安心して学べる魅力ある学校づくりを推進することが重要である」と書かれていた。既に学校に行けなくなってしまった子どもたちへの支援はもちろん、増え続ける不登校の子どもたちを、これ以上増やさないためにはどうしたらよいのか。市、学校、保護者、地域が本気で考え、心から対話できるような場づくりを求める。