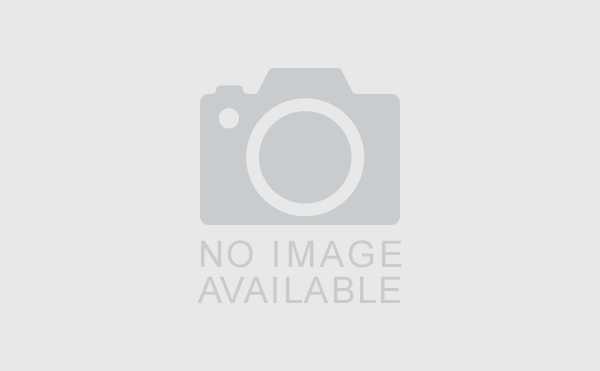小坂まさ代2024年第4回定例会一般質問~1.すべての子どもを大切にした教育を④
(4)経済的困窮家庭の子どもの支援
○小坂「公益財団法人あすのば」では、昨年秋、住民税非課税世帯、生活保護世帯の保護者と子どもを対象とした6,000人調査を実施、平均世帯年収は178万円で、4分の3は貯蓄額が50万円未満、4割は保護者の健康がよくない状態だが、医療機関をほとんど全く受診しない世帯は3分の1、絶望的だと感じたときがいつもある、大抵あるも3割に上る。保護者の9割が困窮の責任が家庭にあると感じ、半数は他者から責められた経験をしているという結果も出ている。精神面に関する以下の質問に、「いつもある」「時々ある」と回答した小・中・高校生は、「何でもないのにいらいらする」48%、「学校に行く気がしない」39%、「孤独を感じる」35%、さらに、「消えてしまいたい」は18%。また、小・中学生のいずれも2割以上が、「学校があまり楽しくない」「全然楽しくない」と感じている。「授業が分からないことが多い」「ほとんど分からない」との答えは小学生20%、中学生38%にも上ったとのこと。この調査の分析によれば、「世帯収入が低い」ほど、「困ったときに頼れる人がいない」が多い、「絶望的だなど心理的ストレスの状態」が高い、「子どもが経済的理由で諦めた」経験が多い、「学校が楽しくない」と感じる子どもほど「生活が苦しいと感じる」が多く、「何もやる気がしない」が多く、「大人が自分の意見を聞いてくれないことが多い」などが判明した。令和6年6月、子どもの貧困対策推進法が改正され、子どもの貧困の解消に向けた対策推進法に変更となった。改正された子どもの貧困解消法では、目的が、貧困により子どもが適切な養育、教育、医療を受けられないこと、多様な体験の機会を得られないこと、権利利益を害され社会から孤立することのないようとなり、より明確化された。貧困の連鎖を断ち切るためにも学習支援は大変重要だと考える。本市では、経済的な理由で塾に行くことが困難な子どもたちに対して、「あ~く学習塾」を実施している。この無料塾の現状について伺う。
○福祉部長
無料学習塾については、子どもの学習・生活支援事業として、経済的な事情で学習塾や家庭教師の利用が難しい小学校3年生から中学校3年生と、中学生から継続して受けている高校生も含めて、学習支援を行っている。またお仕事座談会やバーベキューなどの交流事業、地域イベントの参加を通じ、社会的な居場所にもなっていると聞いている。12月にはクリスマス会を行う予定だとのこと。生活保護世帯を含め、生活困窮家庭を対象に、本町教室、戸倉教室、西町教室の3か所で開校。利用登録者は平均40人前後で推移をしている。これまで小学生が延べ83人、中学生が延べ87人利用。利用についての問い合わせい件数は、小学生が77件、中学生が65件。
○小坂
先日伺い、温かな居場所がつくられている様子を見せていただいた。マン・ツー・マンで丁寧に子どもたちを見てくださっていた。高校生となっても、つながりを柔軟に継続していただいていることにも感謝。こうした支援を必要としている保護者や子どもへの周知はどのように行っているのか。
○福祉部長
生活保護受給者で、対象年齢のお子さんがいる世帯については、生活福祉課の次世代育成支援員が個別に案内や制度の説明を行っている。また、生活困窮者については、自立生活サポートセンターこくぶんじが中心となり、学校校長会、スクール・ソーシャルワーカーとの懇談会での周知、チラシの配架、また地域福祉コーディネーターを通じて地域への発信など、様々工夫しながら周知に努めている。
○小坂
この無料学習塾以外の支援はどのようなものがあるか。
○福祉部長
生活保護世帯を対象に、生活扶助とは、扶助費とは別に、東京都の包括補助を活用した国分寺市被保護者自立促進事業を実施している。具体的には、被保護者の自立につながる経費の一部を支給する制度で、その対象となる経費は様々。その中に次世代育成支援に係る教育関連経費として、上限はあるが給付を行っている。例えば、塾代や高校、大学等の受験費用などが対象となり、令和5年度は27件の実績があった。
○小坂
その被保護者自立促進事業として、渋谷区や国立市が実施している「スタディクーポン」という仕組みがある。これは、経済的な理由で学校外教育を受けることができない子どもたちを対象に、一般の学習塾や習い事で利用ができるクーポン。「現金給付と異なり、使途を教育プログラムに限定できる」「学習、文化、スポーツ、体験活動など、多様な選択肢の中から、子ども自身がやりたいことを選ぶことができる」「大学生ボランティアによる定期的な面談を通して、学習や進路の相談に応じ、安心してクーポンを利用できるようサポートされる」等の特徴がある。この仕組みは、子どもの教育格差や体験格差の解消に有効だと考える。検討を求める。
○福祉部長
他自治体の事例において、どのような効果が得られているかなどの情報収集をまず行っていきたい。