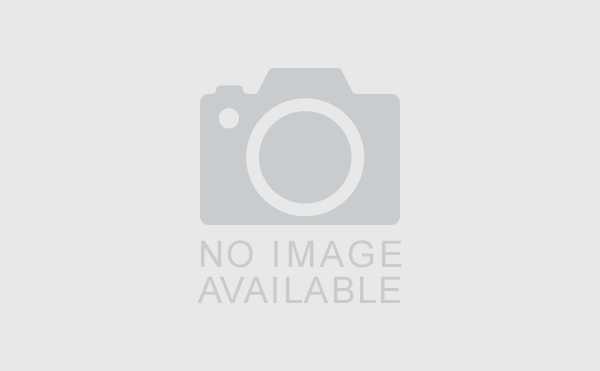小坂まさ代2024年第4回定例会一般質問~1.すべての子どもを大切にした教育を⑤
(5)真の共生社会に向け、インクルーシブ教育の推進を
○小坂
今年度2学期より始まった「インクルーシブ支援員」「エデュケーション・アシスタント」の配置基準と学校での配置後の効果について伺う。
○教育長
「インクルーシブ教育支援員」は、本市では「特別支援教育支援員」という名称。個別支援委員会において、特別支援学校への就学が適当であると判定されたものの、総合的な判断により、小・中学校へ就学した児童・生徒の日常生活上の介助、または学習上の支援を行う支援員を指す。配置基準は、学校1校につき支援員1名の配置。ただし、該当する児童・生徒が3名以上在籍する学校については2名の配置という想定になっている。
実際に配置された学校では、よりきめ細やかなサポートや児童・生徒の交流が深まるようなサポートができるようになっており、当該児童・生徒への支援はもちろんのこと、他の児童・生徒への支援、指導も充実させることができているという報告を受けている。また、「エデュケーション・アシスタント」は、本市では「担任補佐」という名称を使っており、各小学校に1名ずつ、大規模校(二小、四小、六小)には各2名、1学年から3学年までのいずれかの1つの学年に配置をしている。担任補佐の配置により、学習中の支援の充実や児童の安全管理体制の強化などが図られているという報告を受けている。
○小坂
「第4次国分寺市特別支援教育基本計画」によれば、「特別支援教育に関連して障害者理解を推進することにより、周囲の人々が障害のある人や子どもと共に学び合い、生きる中で、社会の構成員としての基礎をつくること、次代を担う子どもに対し、これらのことを率先して進めていくことは共生社会の構築につながるものと考えます」とある。真の共生社会実現のために、共に学ぶことは大変重要だと考える。特別支援学級在籍児童・生徒の通常級との交流の状況について伺う。
○教育長
特別支援学級に在籍している児童・生徒と通常の学級の児童・生徒が活動を共にする機会として、交流及び共同学習を進めている。交流及び共同学習の活動を計画する場合には、保護者も含めて、関係者が互いにその必要性や意義について十分に理解し合うことが前提となり、活動を効果的に実施するために、活動の意義や狙い、交流先の教育内容についてなど、関係者が共通理解をすることが重要。このことを踏まえ、運動会や遠足などの校外学習、また実態に応じて教科学習を通して、交流及び共同学習を進めている。
○小坂
交流を望んでいながらも、1人で通常教に行けない児童・生徒は実際にできていないという場合がある。「インクルーシブ教育支援員」について東京都に確認したところ、令和5年度「特別支援教育推進補助事業」を令和6年度は拡大し、「インクルーシブ教育支援員配置補助事業」となり、「通常級での指導を受けている、または退室した児童・生徒が通常級で学ぶ際や、特別支援学級の児童・生徒が交流で通常学級で学ぶ際に、安心して円滑に学習できるよう支援を行う」となったそうだ。現在は2人しか配置がないが、この制度を活用し、全ての学校に配置し、全ての子どもが交流できるような体制を整えてほしい。
○教育長
「東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助事業」については、4つの補助事業がある。その中のひとつが、「発達障害教育等支援員配置促進事業」である。本市においては、この補助事業を上限いっぱいまで活用し、各学校へクラスアシスタントの基本配置として行っているところだが、また改めて、本事業の趣旨について、各学校に周知を図っていきたい。
○小坂
また、今年度は中学校への配置がない。現在の6年生の状況をしっかりと把握し、新生活でつまずいてしまうことのないよう、新年度からの中学校への配置の準備を、予算も含め、着実に進めていただきたい。
○教育長
特別支援教育支援員については、必要に応じて、先ほどの東京都の補助金等も適切に活用しながら、生徒への支援も行っていきたいと考えている。
○小坂
先月、大阪府豊中市に視察に行ってきた。豊中市では、「共に学び、共に育つ」という理念の下、学校教育や保育においても、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合う共生社会に向けた支援を、全ての子どもたちが同じ場で学ぶことを大切にし、50年近くにわたり進めてきた。重度の障害のある車椅子の子どもも、全盲の子どもも、ダウン症の子どもや発達障害と言われる子どもも、皆同じ教室で学んでいた。子どもを分けないという基本姿勢の下、子ども同士が助け合い、支え合う姿を目の当たりにし、現在の日本の大半の学校が子どもを分けることで見失ってしまっている大切なものの大きさを考える大変貴重な機会となった。障害のある子どもを「取り出す」のではなく、通常学級に「入り込み」をするという仕組み。このように多様な子どもたちが安全で安心して学べるよう、教職員全体で全ての子どもたちを見ていくという共同指導体制は、長年にわたって積み重ねてこられたもので、そのシステムだけを真似するようなことはできない。しかし、真の共生社会の実現には、障害の有無、国籍の違いなど、幼少期から共にあることでしか得られない理解の深さが必要と考える。子どもの「今」だけではなく、「将来」にわたる視点が必要なのではないか。「障害の有無にかかわらず、共に学ぶ」本市としてのインクルーシブ教育について伺う。
○教育長
本市におけるインクルーシブ教育の考え方につきましては、もう既に第4次国分寺市特別支援教育基本計画(義務教育時)におきまして示している。共生社会の形成に向けては、障害のある子どもも障害のない子どもも共に学び合い、生きる中で、子どもたち一人一人の状況を把握し、適切な指導、そして支援を行うことが大切である。そういう積み重ねの中で、やがてはインクルーシブ教育という言葉や特別支援教育という言葉すらなくなっていくということが望ましい姿ではないかと私は考える。これからも真の共生社会の実現に向けて、教育委員会としても努力していきたい。
○小坂
同じ方向を向いていると確認した。
共に学んでこなかった私たち大人は、今、共生社会をつくれずにいる。誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現を子どもたちに託すのであれば、幼い頃から共に学び、共に育つことができるインクルーシブな教育環境を整えていく必要があると考える。今後も議論や対話を続けていきたい。
今回の質問を通じて、様々な支援を必要としている子どもたちがいることを改めて認識をした。中には複合的な困難を抱えている子どももいる。家族丸ごとの支援の必要性を強く感じた。市でも様々な支援策を行っているが、その周知が及ばず、必要としている子どもたちに届いていないということも見受けられる。子どもの周りにいる大人への丁寧な周知と、重要な役割を担うスクール・ソーシャルワーカーなど、支援と子どもをつなぐ役割の方が疲弊することなく仕事を続けていける体制づくりを求める。