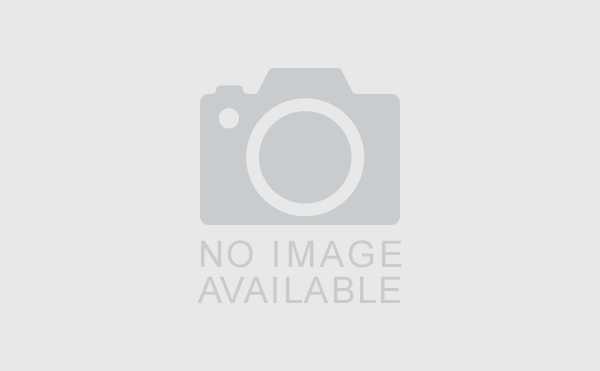小坂まさ代2025年第2回定例会一般質問~1市民との協働を進めていくために (1)提案型協働事業について
1.市民との協働を進めていくために
○小坂
本市議会の議事録を検索してみると、協働という文言が初めて出てくるのが27年前の1998年3月。この間、社会は大きく変化をした。市民との協働について改めて考えたい。
(1) 提案型協働事業について
協働と一言で言っても、その形態は様々で、本市においては、「共催」「実行委員会、協議会」「アダプトシステム」「名義後援」「情報交換、意見交換の場」「事業協力」そして提案型協働事業や公募型協働事業という「委託」と分類をしている。まず、本市における協働事業の考え方と提案型協働事業について伺う。
○市民生活部長
協働事業については、福祉、教育、環境など、複雑化・多様化する地域の様々な課題において、国分寺市自治基本条例に位置づけられているとおり、市民や事業者等と市が対等な立場で能力を分かち合い、共通の目的の実現に向けて協力して取り組むこととしている。現在、市が実施している提案型協働事業については、応募団体の要件等はあるが、市民活動団体の自由な発想で市に事業を提案し、採択された事業について、市と提案団体が協定等を結び、協定等で定めた役割分担、責任分担等に従って、両者が得意な分野を生かして事業に取り組んでいる。
○小坂
昨年度は提案型協働事業について、残念ながら市民団体から提案がなかった。原因分析や、その後の対策について伺う。
○市民生活部長
提案型協働事業については単年度で実施する事業だが、1年ごとに提案し、審査を受け、採択されれば、3回まで継続して実施することができる。残念ながら提案がなかった理由については、継続して提案しなかった事業があったことや、公募型協働事業へ2事業が移行したこと等が原因として考えられる。このことから、次年度の提案型協働事業の募集に当たり、説明会を数年ぶりに実施して、約20名の方に参加をいただいた。実際に事業提案に向けて動き始めている団体もいる。また、新たな取組として、コーディネーターの主催講座「協働をもっと進めよう!」を毎月実施していく予定。市の担当者を交えて、市の事業等を紹介することで、協働の芽を見つけることを目的として、第1回目は「第2次総合ビジョン」について講座を行った。また、市職員においても協働への理解を深めるため、令和4年度からは係長職、令和6年度からは新入職員を対象とした研修を継続して実施している。
今後もコーディネーター等と実施してきた事業を継承、継続するとともに、新たな取組を行うことで、市民側、市側双方に、協働推進の担い手となる人材を育成し、新たな提案が生まれればと考えている。
○小坂
本市の提案型協働事業は、過去に総務省の地方行政改革事例集に取り上げられ、東京都からも高い評価を受けていた。今後も提案型・公募型協働を市民団体と共に、より進めていただきたいが見解を伺う。
○市民生活部長
国分寺市では、これまで紹介した市民活動団体が市に提案する提案型協働事業に加えて、市の担当者が、担当課が事業目的や事業内容の枠組みを定めて、パートナーとなる団体を募集する公募型協働事業の2通り方式がある。市民活動団体が実施する事業について、近隣市の多くが事業費等の一部を補助金として支出している中、当市は、これら提案型・公募型とともに、委託型で行うことで、団体と市が対等な協力関係の下に、それぞれができることを役割分担して取り組み、協働事業を行っている。
今後も人口減少や複雑化・多様化する地域の様々な課題を解決していくために必要な事業と考えている。
○小坂
少子・高齢化が進み、人材の不足が大きな社会課題となっており、行政と市民が手を取り合い、事業運営をしていくことは、今後ますます重要になってきている。本市においては、今のところ人口増は続いているが、市民との協働は一朝一夕に進むものではなく、これまで丁寧に積み上げてきた経験値を、ぜひ今後も生かしていっていただきたい。
応募団体要件や提出書類の見直しなど、市民団体が手を挙げやすいような検討を求める。