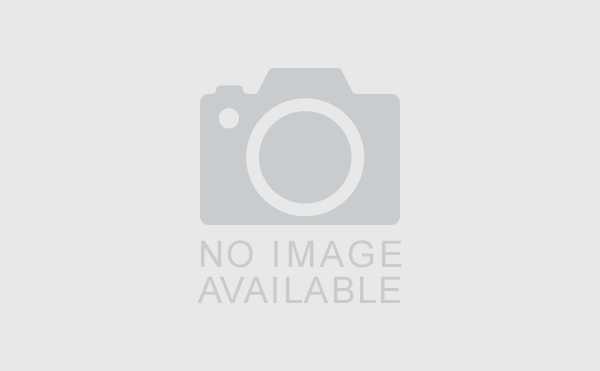小坂まさ代2025年第2回定例会一般質問~1市民との協働を進めていくために (2)公募型協働事業について
○小坂
(2)公募型協働事業について
① 野川源流スクール開講事業(緑と公園課)
市民協働の意義について、またどのように事業を進めているか。
○建設環境部長
この事業は、令和4年度当初、提案型協働事業としてスタートした。国分寺市の貴重な自然の財産と実情を、市民ニーズに沿って、効果的に、もっと多くの市民に知って、見て、感じていただきたいため、4年目の今年度からは公募型協働事業として、提案型協働事業時と同様の内容で引き続き事業を実施していく。
本事業は野川上流域の早期整備に向けて、市民の機運醸成を図ることを目的とし、参加者に野川の実情を知っていただくために行う事業。市民活動団体が作成したテキストに基づき、野川の地理的な概要や成り立ち、生き物、東京都の整備計画、現状などを説明する講座、野川上流端から鞍尾根橋まで現地散策、その後のアンケートなどを実施しており、野川に精通している市民活動団体との協働でなければ実施できない内容である。
○小坂
野川源流スクールにはジュニア版とシニア版があり、ジュニア版は小学4年生を対象に、総合学習の一環として、現在4校で実施をしている。昨年の第2回定例会で丸山議員から、近隣の学校のみならず、市内全校を対象にすることができないかという提案があったが、その後の検討状況について伺う。
○建設環境部長
野川源流スクールは、今後も継続して実施していきたいと考えているので、引き続き関係部署へ本事業の周知を図るとともに、4校以外の小学校で本事業への参画要望がある際には、日程やスタッフの調整等を行っていきたい。
○小坂
国分寺学や環境学習の観点からも非常に有効なコンテンツだと考える。積極的に小学校に提案を。また、今後もボランティアガイドの活躍の場の拡充など、適宜内容を改善しながら事業を継続し、機運の醸成を図るよう求める。
○小坂
②こくぶんじカレッジ協働事業(まちづくり推進課)
市民協働の意義や評価について伺う。
○まちづくり部長
こくぶんじカレッジは、まちづくり条例に基づき設置した市民団体との協働によるまちづくりの支援機関の在り方を見直して、官民連携のまちづくりの視点を取り入れ、企画から立案、実践までの学びを通じて、まちづくりの担い手を育成し、市民主体のまちづくりに発展させることを狙いとしてスタートした協働事業である。中間支援の経験とノウハウを持つNPOと協働で行うことで、市だけではできない、魅力的な事業実施に至っていると認識している。
また、こくぶんじカレッジは今年度で7期目に入り、当初の狙いどおり、こくカレ修了生であるプレーヤーが増え、横のつながりもでき、相乗的にイベントなどに関わる人が増えていっている状況。第6期までで234人の受講生がおり、複数の修了生が、講座修了後にプロジェクトを継続して実践を重ねているほか、地域と修了生が交流する動きも見えている。例えば、市内の農家と共に市民を対象にした収穫体系のイベントを実施する等、講座の枠を超えて、事業実施の効果がまちに還元されていると考えている。
また、修了生の中から支援する側に育った人材もおり、NPOの新陳代謝も生まれている。このようなことから、市としては、人を発掘して育てているという成果がしっかり出ていることを評価できると考えている。
○小坂
市内を回っていると、あちらこちらで修了生の方のイベントに出会うことが多くあり、この事業の効果の大きさを感じている。修了生が運営側に回り活動を続けていることも、人材発掘・育成の観点から大変評価できる取組だと私も考える。
こくカレから生まれたこくフェスが先週末に開催をされた。私もボランティアで参加したが、土曜日が雨天だったため、5か所が中止となったものの、4回目を迎えた今年は、33もの会場で実施をされ、まさに街中に音楽があふれた2日間だった。昨年の参加者数は1万6,500人だったと聞いている。これほどの規模の音楽フェスが市民の力で成し遂げられ、そのきっかけが市の協働事業であるこくカレであったことに、改めてこの事業の意義を深く実感をしたところである。NPOだけではなく、行政の職員がしっかりと関わることで、参加者の様子や活動内容が把握でき、意見交換をしながら、年を重ねるごとに、よりよい事業に育っていると認識をしている。今後も協働の意義や重要性について考え続けていっていただきたい。また、経済課の空き家・空き店舗活用事業のように、関係各所と連携しながら、修了後の活動の場についても支援をお願いしたい。
○まちづくり部長
現在、NPOとの協働事業により、まちづくりの担い手の育成が進み、協働事業としての一定の成果が出ているといった状況。市が考える、より望ましいやり方としては、市が主体ではなく、市の関わりは最小限の手助けにとどめ、NPOがより活動の厚みを拡大し、自走できる基盤を構築できることと考えている。今後、市の支援体制については、NPOの力量に応じて見直しを行いつつ、市とNPOが互いに協力し、この事業を発展させていきたいと考えている。また、修了生の支援については、今後も活躍の場が広げられるよう、関係部署、関係団体と連携し、支援を継続していきたい。
○小坂
発表の場である「こくぶんじスパイス」も見学したが、興味深い取組が毎年生まれている。提案型協働事業にふさわしいものがあった場合には、まちづくり推進課が伴走し、翌年応募するといったことも考えられるのではないか。
このNPOは拠点が国分寺駅近くにあり、独自の事業でも地域で活動する市民の支援をしている。今後については、これまで協働という形で進めてきた取組を評価した上で、市にしかできないこと、NPOだからできることを踏まえ、検討していっていただきたい。
③ 国分寺市親子ひろば事業(子育て相談室)
○小坂
市民室内プールで実施している親子ひろば事業は、平成28年4月より公募型協働事業として委託をしている。様々な運営方法がある中、公募型事業としている理由と、どのような点を大切にしているのか伺う。
○子ども家庭部長
現在、市内の12か所で親子ひろばを実施しているが、運営形態の内訳は、市の直営が2か所、指定管理による委託での実施が5か所、指定管理以外の委託での実施が4か所、そして公募型協働事業での実施が1か所となっている。
親子ひろばについては、定期的に実施事業者が集まる連絡会を開催しており、各広場の取組について情報共有を図ることで、さらなる事業の推進に役立てている。特に公募型協働事業については、団体が持つ独自の強みや地域性、柔軟性、住民とのつながりを生かした活動などが行われることを期待している。
○小坂
こちらのNPOは、「子育てに困ったら、そこにサードハンドがある」というモットーを掲げ、国分寺地域を中心に子育て支援をしている。親子ひろば事業を18年にわたって手がけている団体の専門性は高く、パパカフェ、異文化カフェなど、利用者ニーズにスピード感を持って対応しているほか、地元での担い手育成などもしていると認識をしている。今後も連絡会を通じて各事業者のよい事例を共有していっていただきたい。
④国分寺市両親学級及び育児学級事業(子育て相談室)
○小坂
なぜ、今回、市の事業を直営から公募型協働事業としたのか。
○子ども家庭部長
これまで講座や交流会などを実施する両親学級や育児学級の場を活用して、支援が必要な方を把握し、支援につなげてきた。しかし、令和5年度から出産・子育て応援事業が本格実施により、伴走型相談支援によって、妊婦やその家庭を把握する機会が増え、両親学級や育児学級以外の事業でも支援対象者を把握することが可能となったことから、事業の実施方法等について整理をし、両親学級等による講座や交流会の実施は委託事業者が担い、市は支援が特に必要な妊婦や、その家庭への伴走型相談支援を中心に実施することとした。委託に当たっては、令和3年から5年度まで実施した提案型協働事業、多職種による妊娠期からのサポート事業の実績を踏まえて、地域資源を把握している団体からの提案によって、妊婦やその家庭が参加しやすく、参加者同士が交流しやすく、また地域交流が促進できるような事業とするため、公募型協働事業として実施することとした。これによって、よりよい事業を実現できると考えている。
○小坂
これからも団体と連携し、産前産後の切れ目のない支援体制の推進をお願いしたい。
今回、質疑するに当たり、これまで協働事業に関わられた方々にヒアリングをさせていただいた。「担当課とのマッチング」や「担当の職員と市民団体とのコミュニケーション不足」「コーディネーターの関わり方」「市民目線での横断的な提案に対して、担当課が対応できていないのではない」「協働コミュニティ課には、協働期間中も担当課とうまく事業が進められているか市民団体にヒアリングし、進められていない場合はサポートをしてほしい」などのご意見をいただいた。
提案型については、初年度は協働コミュニティ課が所管の担当となり、実際の事業に関わる課はサポート課として事業を進めていくことも考えられるのではないか。ぜひ、こうした声を生かし、市民と共に、さらなる協働のよりよい仕組みづくりについての検討を求める。