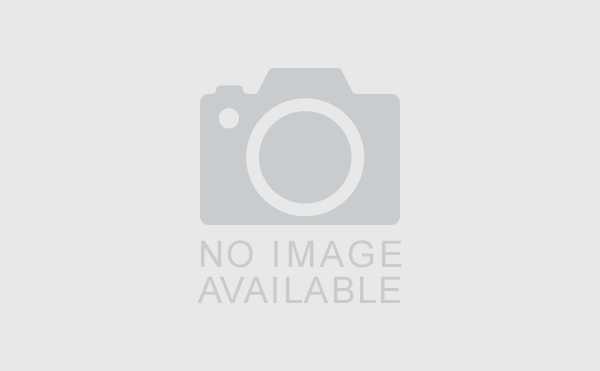小坂まさ代2025年第2回定例会一般質問~1市民との協働を進めていくために (3)公民館における協働事業について(4)学校キャンプについて
(3)公民館における協働事業について(公民館課)
○小坂
公民館は地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割を果たしている。地域全体で学びを深め、地域社会を活性化していくためには、市民との協働が不可欠だと考える。現在、公民館が行っている協働事業の種類と、その意義について伺う。
○教育部長
公民館の協働事業の種類は、実行委員会や企画委員会を立ち上げて行うもの、地域会議や公民館運営サポート会議、コミュニティ・スクールとなった小・中学校との共催で行うものがある。また、公民館と自主グループとの共催のグループ企業事業や自主グループの日常活動を紹介するグループ活動公開事業を実施している。それにより、参加者に活動の場を提供し、共に学ぶ機会の拡充を図っている。
○小坂
コロナ禍前と比較して、公民館で行っている協働事業の件数はどのように推移しているか。また、今後の展望についても伺う。
○教育部長
コロナ禍前の令和元年度は30事業を実施。コロナ禍である令和2年度から令和4年度は9事業、31事業、42事業の実施となりました。その後、コロナが感染症法上の5類感染症に位置づけられた令和5年度については49事業、令和 6年度は58事業を実施。コロナ禍前と比べて、協働事業の件数は増加している状況。今後については、これまでの協働事業のほか、中学校区ごとに公民館が設置されている特性を生かし、コミュニティ・スクールとなった各学校との協働事業の充実を図っていきたい。
従前から、恋ヶ窪公民館では近隣の小学校と連携し、第五小学校のサマースクールや第九小学校の夏のわくわく学校に参加してきた。今後も地域の学校と連携し、実施していきたいと考える。
○小坂
特にPTA連合会解散後の保護者団体との共催事業の継続を求めておく。
(4)学校キャンプについて(社会教育課)
○小坂
学校キャンプは、学校施設での非日常的な体験、豊かな地域コミュニティを形成することを目的として、地域住民と学校、行政が協力や連携をし、市教育委員会の事業として、市立小学校全校で夏休みの催しとして実施されていた。令和2年度より主催が地域団体となり、令和2年度は4校、令和3年度は5校、令和4年度以降は8校で実施されている。コロナ禍であっても地域の方が中心となり試行錯誤し、子どもたちのために実施していただいているが、残念ながら 2校で開催できていない。まず、市として、この事業の重要性をどのように捉えているか伺う。
○教育部長
学校キャンプは、地域の特性を生かした取組として地域の方々が主体となり、実行委員会を組織して実施している。地域が主体となって実施することにより、子どもたちは仲間や地域の方々との触れ合い、体験を通じて豊かな人間性を育むとともに地域について理解を深め、地域に愛着を持つきっかけともなり、豊かな地域コミュニティの形成にもつながるものと考える。また、地域コミュニティの醸成は、希薄化が進む地域社会の課題解決や災害時における共助の力にもつながることから、学校キャンプを継続して実施する意義は大きいと考えている。今後も地域の方々が主体となる形で事業を支援していきたい。
○小坂
現在、各校実行委員会と連携をどのように図り、どのようなサポートを行っているか。
○教育部長
各学校の実行委員会の皆さんとは毎年意見交換会を開催し、実施予定等の共有やキャンプ物品の貸出し、安全管理上の留意点などについて情報共有を行っている。教育委員会では、実行委員会が安全かつ円滑に運営できるようテント等の備品の貸出し、参加児童や指導者に対する保険対応、当日の警備支援など、必要なサポートを行っている。
○小坂
実行委員の方々もテントの手入れに協力していただいていることも確認させていただいている。毎年委員が入れ替わる学校もあり、各校の実行委員会がより活動しやすいよう、今後も支援していただきたい。学校長は他の自治体から着任される方もいるので、学校側との潤滑油となり、この事業の重要性について御理解いただけるよう説明をお願いしたい。校長会やコミュニティ・スクールの打合せなどの場を活用し、今後全校で実施できるよう後押しをお願いしたいが、いかがか。
○教育部長
学校施設を利用して実施する本事業においては、学校との連携、協力が不可欠であり、学校長の異動等により体制の変化があったとしても継続して実施する必要があると認識している。これまでも定例校長連絡会などの場を活用し、各学校での実施内容やスケジュール等を共有し、本事業への理解促進を進めてきたところ。今後もこうした場を活用しながら学校との情報共有をし、コミュニティ・スクールの連携も意識した当該事業への理解、協力を深め、実行委員会の皆さんが円滑に事業を実施できるように努めていきたい。
○小坂
長年学校キャンプに関わっている委員の方からは「警備員の方を派遣してもらえて心強い」「安心して開催できている」「困り事を聞いて寄り添った対応をしてくださっている社会教育課の職員の方に感謝している」といった声が寄せられている。今後コミュニティ・スクールを進める上でも重要な行事になると考える。引き続き丁寧な連携を求める。
今回、様々な形の市民協働について伺った。本市において市民協働が「自治基本条例」や「まちづくり条例」にしっかりと位置づけられ、進められてきたものであることを改めて確認できた。本市の協働推進ハンドブックの冒頭には、協働を進める目的として「真の市民自治を確立すること」、「市民自治を拡充し、そのことを市民自身が実感すること」とある。市民が主体的に生き生きと生きるためにこうした協働事業が非常に重要であることは、今回多くの方からお話をお伺いし、確信した。少子高齢化の進行により福祉、教育、環境、防災、防犯など広い分野で地域社会の課題が存在していること、生活様式の変化により市民の地域社会に対する関心の希薄化が進んでいること、また、今後厳しい財政状況の中で持続可能な市政運営を行うには、地域課題の解決に向けて市民と市が一体となって共に汗を流し、地域をつくる協働のまちづくりを進めていくことがこれまで以上に必要になってくると考える。協働コミュニティ課が中心となり全庁的に市民との協働の意識を高めていっていただきたい。