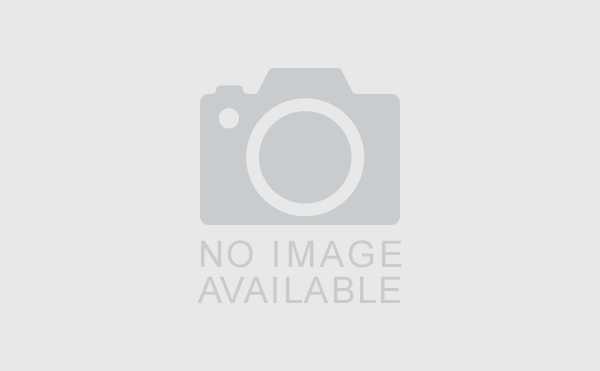小坂まさ代2025年第2回定例会一般質問~2.学校における子どもたちへの特別な支援について
2.学校における子どもたちへの特別な支援について
○小坂
(1)市立小・中学校の今年度の特別支援学級と特別支援教室の状況について
過去5年間の児童・生徒数の推移と今年度の状況について説明を。
○教育部長
令和7年度も通常の学級に通う児童・生徒数が増加傾向にあることと同様に、特別支援学級も小学校、中学校ともに増加傾向が続いていると捉えている。
○小坂
今年度の小学校における知的障害学級に在籍する児童数も、依然100名近くいるのではないか。知的障害特別支援学級の増設については、4月の教育委員会で令和8年度に第六小学校に開設されると明言された。現時点での増改築の予定、受入れ人数、保護者への周知など、スケジュールについて伺う。
○教育部長
4月の教育委員会定例会では、令和6年1月に公表した国分寺市立小学校知的障害特別支援学級設置等検討委員会報告書に基づき、市立第六小学校に特別支援学級の開設準備を始めるという報告をさせていただいた。その検討委員会から、「市内の児童数の推移を十分注視しながら、既存の教室の活用や新規の教室の増築等を視野に入れ、新規に特別支援学級を設置することが可能な学校を決定していく必要がある」との報告を受け、全体の児童数の動向を注視してきた。それに鑑み、第六小学校への開設準備を進めるというもの。ただ、現時点において教育委員会に諮り承認されているものではないため、詳細については改めて報告させていただくとともに、保護者等への丁寧な説明を遅滞なく行っていきたいと考えている。
○小坂
該当される地域の方にとっては、二小か六小、どちらの学校に通うのかは、通学経路や兄弟児との関係から見ても非常に大きな問題。また、どのような教育環境になるのかも分からないのでは、さらに不安が高まるのではないか。来年度からということで、できるだけ早い説明をお願いしたい。就学・転学する可能性がある方を対象とした特別支援学級説明会が各校で間もなく開始される。第七小学校けやき学級、5月16日、第二小学校わかば学級、6月27日、第四小学校双葉学級は7月2日とのこと。重ねてになるが、できるだけ早く保護者の方たちへ詳細を説明していただけるよう強く求める。
さて、今年度の四小さつき学級の児童数は50名を超えたと聞いた。この5年で小・中学校とも自閉症・情緒障害支援級在籍児童生徒数は約2倍になっている。増加傾向が続く自閉症・情緒障害支援級の増設についても、今後検討が必要なのではないか。検討状況と、5月9日まで委員の募集が行われていた特別支援教育推進委員会について説明を。
○教育部長
自閉症・情緒障害特別支援学級の児童数が増加傾向であることは認識している。本市では、今後これまでの第4次特別支援教育基本計画の推進状況を確認し、その成果と課題を踏まえ、特別支援教育推進委員会において令和8年度以降の特別支援教育の充実に向けて検討していく予定である。小・中学校の自閉症・情緒障害特別支援学級の増設については、論点の一つとなると考えている。
○小坂
4月の教育委員会の資料によれば、10月までに全5回の委員会を実施し、12月にパブリック・コメント、来年1月に教育委員会への議案提出というスケジュールになっていた。短期間ではあるが、有識者、保護者や公募市民の方を交えた深い議論が行われることを期待する。続いて、クラスアシスタント、介助員、特別支援教育支援員について、新年度に入り、必要な子どもたちに配置できているのか伺う。前年度から学校に要望しているにもかかわらず、つけてもらえないという声が毎年この時期にこちらに寄せられる。新学期の配置状況について確認させてほしい。
○教育部長
特別支援教育支援員については、必要な児童・生徒が在籍する学校に配置できている状況。クラスアシスタントと介助員については、これまで勤務していた方々が退職されたことや特別支援学級の学級増などがあり、幾つかの学校において数名の配置ができていない状況。現在、できる限り早期に人員が確保できるよう、学校と関係課と連携して対応しているところ。
○小坂
新しい学校での生活に困り事を抱える子どもの保護者の方から、私たちへの相談が後を絶たない。新年度にしっかりとしたサポートがなかったゆえに不登校に至ってしまう事例もあった。環境が大きく変わり、子どもにとっての負担が一番大きい4月から支援員を配置ができるよう、今の仕組みで難しいのであれば、仕組みの改善の検討を東京都に働きかけるなど、考えていただきたい。
(2)学校生活支援シートと個別指導計画について
○小坂
「学校生活支援シート」は、4月の入学後速やかに作成することで子どもが新しい環境での困り事を減らすことができると考える。各校でどのように作成されているのか、また「就学支援シート」との違いについても伺う。
○教育長
「学校生活支援シート」については、小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒や特別支援教室や通級による指導を利用している児童・生徒について、入学後、必ず作成している。また、通常の学級に在籍している児童・生徒についても、必要に応じて作成している。保護者、学校、関係機関がそれぞれの役目を確認しながら必要となる支援を行っていくために作成しており、学校卒業後まで一貫性のある支援を行うために活用している。
「就学支援シート」については、幼稚園や保育所などの就学前施設に在籍する幼児について、保護者の希望により作成するもの。保護者、就学前施設、関係機関が協力して作成しており、一人一人の幼児が新しい環境でも今まで培ってきた力を十分に発揮できるよう、就学前の支援について小学校に引き継ぐ資料として活用している。各学校においては、新年度の早い時期に学校での様子などを把握した上で、保護者と相談して学校生活支援シートを作成している。特に小学校の入学に際し「就学支援シート」の提出があった児童については、その内容を「学校生活支援シート」に反映させるようにしている。
○小坂
どちらも支援が必要な子どもが合理的配慮を受けるためにとても重要なツールだと考えている。こちらには、通常級在籍の手帳の交付を受けている児童の保護者から、4月末になってもまだ支援シートの作成について学校側から話がないと相談があった。その後学校に問い合わせたところ、通級の利用や特別支援学級在籍の児童以外は保護者からの申出がないと作成はしないと言われたとのこと。このシートの存在や仕組みについて知っている保護者の方はそう多くはないのではないか。こうしたシート作成のやり取りがあることで、学校と保護者との話合いがスムーズにいくと考える。特別支援教育を現在受けているお子さんの保護者だけではなく広く周知をし、支援を必要としている子どもたちが取りこぼされないよう求める。
続いて、「個別指導計画」について伺う。こちらは、どのような時期にどのように作成されているのか。
○教育長
個別指導計画については、学校生活支援シートに示された学校の指導支援の中で、学習に関する支援を具体化したもので、学校生活支援シートとともに年度当初に作成するもの。しかし、特別支援学級や特別支援教室に年度途中で入級や入室した児童・生徒、また年度の途中で保護者との相談の上で作成が必要となった児童・生徒については、その都度作成している。
(3)保育所等訪問支援事業について
○小坂
こういった学校生活支援シートや個別指導計画作成に当たっては、障害についての専門的な知識を持った方からの目線も必要なのではないかと考える。そうした方が学校現場に入れる仕組みとして保育所等訪問支援事業がある。この事業は、保育所、幼稚園、学校などに在籍している18歳までが利用できる仕組みとなっている。どのような事業なのか、また学校での利用と現状について伺う。
○福祉部長
保育所等訪問支援事業は平成24年の児童福祉法改正により創設された障害児のためのサービスの一つ。障害児が保育や教育等集団生活で安心して過ごすことができるよう、普段通っている場に専門的知識のある支援員が訪問し、環境整備支援を行う事業。保護者からの相談、申請に基づき市が支給決定を行っており、昨年度の市立小学校への給付は数件。必要な方にぜひ利用いただきたい。
○小坂
集団での生活や適応に専門的支援が必要であれば、診断や障害者手帳の有無に関係なくこのサービスを受けることができ、利用するには通所受給者証の取得が必要になるが、受給者証の申請には診断書は不要とのこと。利用負担は9割が自治体、1割が利用者負担となっている。比較的新しいサービスであり、まだほとんど知られていないのではないか。保護者が個別に学校等に働きかけることにより利用がスタートできると聞いているが、学校側から「そのような支援は知らない」と言われた方もいるよう。この事業は子どもを支援するだけではなく、日頃子どもに接する教員や支援員の方も支援する意味合いのある事業で、学校にとっても負担軽減になることをご理解いただく上でも、学校現場を含め広く事業の周知が必要だと考える。見解を伺う。
○福祉部長
市の障害福祉ガイドブックにおいて市内の事業者情報を掲載している。年1回情報を更新し、ホームページでもご覧いただける。このサービスについては、特に集団生活に出向くアウトリーチ型のサービスであり、保育所、幼稚園、学校等、受け入れていただく集団生活の場で理解いただくことが重要と考えている。事業者、関係者への情報提供、定例校長連絡会での説明など、効果的な周知に取り組んでいきたい。
○小坂
(4)就学相談について
昨年も、一昨年もこの第2回定例会で就学相談について質疑した。一部提案を受け入れていただき、説明資料を市HPに掲載し、今年度は音声入りスライドデータにしていただいた。今後も読む方の気持ちに寄り添った表現やデザインに工夫していただけるよう求める。さて、昨年度、就学相談の締切りを2か月前倒しし、7月31日とした。そのことで改善された点について伺う。
○教育長
就学相談の締切りを9月末日から7月末日へ変更したことで、特別支援学級や特別支援教室の授業見学や説明会への参加案内を2学期開始に合わせることができた。これにより、保護者が就学先を検討する時間にゆとりを持てたということが考えられる。また、就学に関する相談、必要書類の準備、判定に係る審議等について、年度末までに確実に実施することができたことは成果と捉えているところ。
○小坂
昨年の決算特別委員会で、本市のホームページ上で「就学相談は時間がかかります。7月末までにお申込みください」と書かれ、8月1日には更新され、「令和7年度入学の相談受付は終了しました」と赤字で大きく出ていることを指摘した。「少しだけでも読む側に思いをはせていただき、表現を工夫してはいただけないか」と、他市の事例を紹介し要望したところ、文言はそのままで青い字に修正されていた。
「お気軽に御相談ください。」「共に考えていきましょう」といった表現に救われる思いの保護者がいる。ホームページの表現の工夫を引き続き要望する。