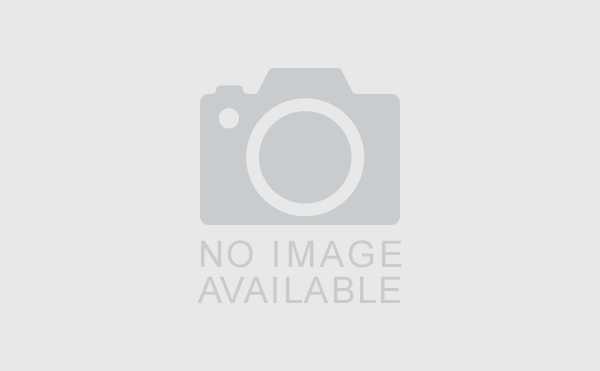小坂まさ代2025年第2回定例会一般質問~3.こども家庭センターについて
3.こども家庭センターについて
○小坂
こども家庭センターが開設して約1か月が経過した。児童福祉と母子保健が一緒になったことで効果を感じていることや、大切にしていることはどのようなことか。
○子ども家庭部長
機構改革によって、令和6年度より児童福祉と母子保健が同じ組織にはなったが、それぞれ別の場所に執務室があった。令和7年4月より執務室も一緒になり、これまでやり取りは電話等で行っていたが、対面で随時やり取りできるようになった。また、昨年度より児童福祉と母子保健の職員で構成する合同ケース会議を開催しているが、その合同ケース会議以外の場合でも必要に応じて随時関係の職員が集まって、打合せがスムーズにできるようになった。こども家庭センターの開設によって連携は強化されたと感じている。今後は、さらなる児童福祉と母子保健の一体的な支援の構築に努めていく。
○小坂
連携が強化されたとのこと、大変心強く思う。
妊娠期からの切れ目のない支援をきめ細やかに実施するために、本市では妊娠期に「ゆりかご・こくぶんじ面接」、産後に乳児家庭全戸訪問事業「こんにちは赤ちゃん事業」を行い、該当されるほぼ全員に近い方に保健師や助産師の方が会っているため、支援が必要ではないかと思われる方にアウトリーチできる仕組みがある。一方で、子どもの虐待死など痛ましい報道が後を絶たず、自治体間の転出入を繰り返し、支援の仕組みから漏れてしまっている事例も見られる。本市において、転入家庭への子育て支援への案内についてどのような工夫がされているのか。例えば子育て世帯の方が手続に来た際に子育てガイドの「ホッとおれんじこくぶんじ」を渡すだけではなく、悩み事相談ページを担当課から一言お知らせするような連携が考えられるが、いかがか。
○子ども家庭部長
当市では、要保護児童対策地域協議会を設置しており、支援を必要とする家庭に対して、協議会の調整機関であるこども家庭センターが中心となって庁内の関係部署、関係機関と連携を図り、支援を必要とする家庭への支援を行っている。転出入のケースの場合には転出先、または転入元の自治体と密に連携を図って、支援から漏れることがないよう対応している。今後も子ども家庭センターが中心となり、支援が必要な家庭への適切な支援を行っていく。また、支援を必要とする方へ相談窓口などの情報が行き届くよう、提案の件についても、関係部署との連携も含めてさらなる周知方法について研究していく。
○小坂
転入された方の目に子育てガイドが触れるよう、2階フロアだけではなく、1階の市民課窓口近くにも配架するなどの検討もお願いしておく。