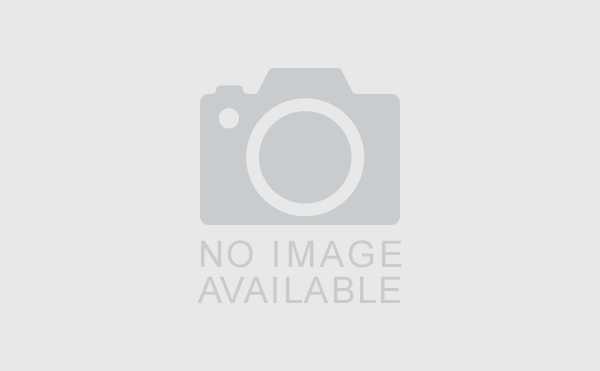小坂まさ代2025年第3回定例会一般質問~2.自殺対策について (1)子ども
2、自殺対策について
〇小坂
2023年第4回定例会でも、生きる支援を全力でと題し、国分寺市の自殺対策について質問したが、その際には、コロナ禍を経て、若者と女性の自殺が増え、国分寺市の自殺死亡率は、2020年以降、東京都の平均値を上回り、やや高い水準で推移をしていた。現在の国分寺市の自殺者数や自殺死亡率の状況について伺う。
〇健康部長
厚生労働省のホームページで公開されている自殺の統計、地域における自殺の基礎資料、令和6年によると、国分寺市の令和6年の自殺死亡者数は11人、人口10万人当たりの自殺者数で表される自殺死亡率は8.54となっている。令和5年の本市の自殺死亡率が14.04だったので大幅に低下した。令和6年の全国の自殺死亡率は16.11、東京都が15.53となっている。国や東京都と比較しても低い状況。改善した要因等については、今後、分析を進めていく。
〇小坂
それでも昨年11名もの方が自ら命を絶っている現実がある。一つの命が失われても、自殺死亡率は大きく上昇し上昇する。それよりも何よりも、かけがえのない命を失われる要因を少しでも減らしていかなければいけないと考える。厚生労働省のホームページによれば、令和4年の全国の自殺死亡者数は2万1,881人、令和5年、2万1,837人、令和6年、2万320人と減少傾向にある中で、子ども、特に女子中高生の自殺が増加をしている。第2次国分寺市地域福祉計画の中でも、特に子ども、若者、女性の支援を充実・強化するとある。
(1)子ども
①こそでん、子ども専用相談電話
〇小坂
国分寺市では、子どもの悩み相談先として、子ども家庭センターの子ども専用相談電話、(通称)こそでんが平成21年に開設をされた。子どもたちへの周知方法と、コロナ禍以降の相談状況について伺う。
○子ども家庭部長
こそでんは、18歳未満の子ども向けの無料相談電話です。毎年、市内の公立小・中学校の全児童・生徒に、こそでんを周知するカードを配布し、子ども家庭センターの職員が各学校を訪問し、接子どもたちに昼休みの放送などを通じて説明を行っている。昨年度は16件の電話があったが、多くが人間関係の相談だった。相談のほとんどは1回で終了いているが、複数回相談する子どもも。こそでんの受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までで、子ども家庭センターの職員が対応しており、受付時間外の対応としては、周知カードに夜間や休日でも相談できる東京都などの相談窓口を掲載している。
〇小坂
東京都では、子ども政策連携室による、ギュッとチャットという小学生から大人までチャットで相談できる仕組みが今年から始まっている。悩みや不安を抱える子どもや保護者が専門的な相談機関につながる前に、最初の一歩として無料で利用できるサービス。こちらの情報も、ぜひ掲載の検討を。また、相談はほとんどが1回で終了とのだが、こそでんでキャッチした子どもの声が必要な支援につながるよう連携を求める。このほかに、子ども家庭部では子どもへの対策の取組はどのようなものがあるか。
〇子ども家庭部長
自殺対策に特化した事業ではないが、各種相談事業や子どもの居場所となっている児童館などにおいて、子どもが困ったときに助けを求められるよう、話しやすい環境づくりに努めている。職員は家庭や学校以外の第三者という立場で子どもの話を聞き、必要に応じて相談や助言ができる存在となっている。こうした存在の働きかけが自殺予防の取組にもつながると考えている。また、心配な子どもを把握した場合は、学校や子ども家庭センターなど、必要な機関と連携し、適切な支援につなげている。
〇小坂
親でも先生でもない、斜めの関係の大人の存在が非常に重要だと考える。相談や児童館につながっていない子どもたちが気になるところ。また、学校との連携も非常に重要。多くの学校で新学期が始まる9月1日、18歳以下の子どもたちの自殺が1年で一番多い日である。2024年の小・中高校生の自殺者数は529人、1980年の統計開始以来、過去最多となってしまった。動機は学業不振、学友との不和、いじめ等学校問題が多く見られるとのこと。そこで、学校での取組について伺う。
②SOSの出し方に関する教育
〇小坂
文科省は本年2月28日付で、「児童・生徒の自殺予防に係る取組」についてという通知を発出。SOSの出し方に関する教育について、以下のように記載がされている。「児童・生徒自身が心の変化や危機に気づき、身近な信頼できる大人に相談できる力を養うとともに、児童・生徒が安心してSOSを出すことのできる環境の整備に努めること」。SOSの出し方に関する教育とは、どのような授業なのか。
また、2月28日に続き、再度6月30日にも同様の通知が文科省から発出されているが、これを受けて、どのような指導が各校で行われたのかも併せて伺う。
〇教育長
児童・生徒の自殺予防に係る取組について、東京都教育委員会が作成したSOSの出し方に関する教育を推進するための指導資料などを活用し、全校で保健体育科や道徳、特別活動の授業で夏季休業前に指導を行うこととしている。例えば、小学校5年生の保健の授業では、不安や悩みへの対処をテーマとして、指導資料の映像教材やワークシートを活用して、不安や悩みの概要について知り、つらい気持ちになったときに、どのように対処するか、児童が考えて、お互いに伝え合う取組も行ったところ。また、文科省の通知を受け、夏季休業中の生活指導について、各学校に通知をした。各学校では、児童・生徒が休業期間中も心身ともに健康で安全に生活できるよう、一人一人の児童・生徒の実態に応じたきめ細かな指導や支援を組織的に行うよう努めたところ。さらに各学校では、児童・生徒に国や都、市の相談窓口を一覧にした資料をGIGAスクール端末で配布するとともに、不安や悩みがあるときは、いつでも相談できること、長期休業前に学級担任等が指導している。加えて、ウェブアンケートを用いた心の健康観察を実施したり、困っていることや悩みなどを自由に話せるポストを設置し、GIGAスクール端末からの投稿も可能にしたりするなど、各学校が実態に応じて工夫して、子どもの声を受け止める支援体制を整えている。
〇小坂
様々な試みをしていることは理解するが、子どもたちの側に、「あなたが助けを求めるようになりなさい」というメッセージを伝えていないかというような思いもある。命の大切さを教えるとともに、命を大切に思えない子どもたちに対して、安心してその思いを吐き出せる、そうした場や聞いてくれる大人の存在が必要なのではないか。受け止められなかったSOSは大人への不信感を深め、子どもたちが心を閉ざしてしまうことにもつながりかねないと危惧している。そこで、子どもたちから発せられたSOSを確実に受け止める体制について伺う。教員や保護者などへの大人への研修や周知について、どのように実施されているのか。
〇教育長
教職員が児童・生徒のSOSを受け止め、支援する力を向上させていくこと、このことは極めて重要である。学校では児童・生徒のサインを見逃さず、適切な支援につなげられるために、東京都が作成したリーフレットなどを活用して研修を行っている。加えて、保護者には子どものSOSの受け止め方を相談できる窓口一覧を学校が配布し、紹介をしている。今後とも学校が保護者や関係機関等とも連携をし、組織的な対応を図ることができるように支援をしていきたい。
〇小坂
8月25日から昨日までcocobunjiプラザで開催されていた「心と体を傷つけられて亡くなった天国の子どもたちのメッセージ展」を拝見した。子どもたちの写真や言葉、遺族のメッセージに胸が締めつけられる思いがした。子どものSOSを受け止める教員の負担を軽減するため、身近に相談できる大人の確保、常駐のスクールカウンセラー配置の検討も要望する。
③学校でのメンタルヘルスケアの学習について
〇小坂
学校を対象とした調査では、子どもが抱える心の健康問題が多様化・深刻化しており、近年の保健室の利用件数についても、心の問題が体の問題を上回るという調査結果が出ているとのこと。子どもたち自身が自分の心の状態について知ることはとても重要になっている。子どもたちはメンタルヘルスケアについて、現在どのように学んでいるのか。
○教育長
学校では、学習指導要領に基づき、メンタルヘルスケアという言葉は使用していないが、小・中学校での保健の学習の中で、心の健康として扱っており、児童・生徒は教科書を中心に学んでいる。例えば、中学校1年生では、体をほぐすなど心身をリラックスさせることや規則正しい生活を送ることなど、ストレスへの対処方法を具体的な事例を基に理解するとともに、リラクゼーションの方法について学び、実践するといった学習をしている。
また、信頼できる大人に相談することの大切さについても学んでおり、学校では、担任だけではなくて、学年主任、養護教諭、他の学年・学級の教員、またスクールカウンセラーなど、児童・生徒が誰にでも不安や悩みを相談してよいことを伝え、安心して学校生活を送れるようにしている。加えて、特に小学校5年生、中学校1年生には、スクールカウンセラーによる全員面接を実施して、相談しやすい環境の整備にも努めている。
〇小坂
気になるのは、不登校児童・生徒にこうした学びを届けることができているのかどうかということ。学校に行けないこと自体がSOSの発信である。引き続き不登校の子どもたちへの支援の拡充を要望する。
令和6年度子どもの自殺の多角的要因分析に関する調査研究報告書には、子どものSOSは「死にたい」という言葉に限らず、登校渋りや自傷、気分の落ち込み、態度の変化など多様に表れるとある。後書きでは、制度整備に加え、日常的に子どもと接する全ての大人が発言や行動の変化に心を配り、寄り添い、連携して支えることの重要性が強調されていた。1人で悩まずに、分かち合える人がいると感じてもらえることが命をつなぐ力になるという言葉に深く共感した。私も周囲の子どもに寄り添い、声を聞かせてもらえる大人であるよう、考え続けていきたい。