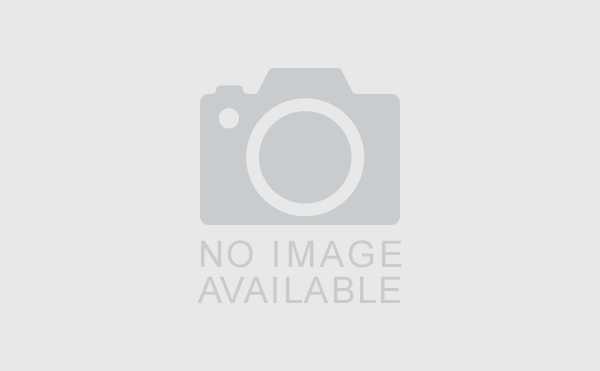小坂まさ代2025年第3回定例会一般質問~2.自殺対策について (2)若者(3)妊産婦 (4)高齢者 (5)生活困難者
(2)若者について
〇小坂
10代の死因第1位が自殺であるのは、先進国G7の中では日本だけである。厚労省のホームページによると、本市において、今年に入ってからの自殺者数は3名、そのうちの2名は20代の方。2023年3月の予算特別委員会では、国分寺市若者支援地域ネットワーク会議において、支援者向けリソースマップの活用について触れられていたが、その後の運用状況や若者に対する具体的な対策の進捗、現状について見解を伺う。
〇子ども家庭部長
若者支援相談事業において、相談しやすい環境づくりを昨年度から工夫して行った。「相談」という見出しでの広報は、お困りの方からすると敷居が高いという声を受け、「おはなし処」という名称で広報し、相談を受け付けたところ、相談の件数が増加した。件数が伸びることだけが決していいこととは考えていないが、相談者からの感想で、「おはなし処」という名称が相談しやすい環境になっていることを確認できた。おはなし処については、相談件数も伸びたことから今年度も継続で実施をしている。いただいた相談については、国分寺市若者支援地域ネットワーク会議の連携を活用し、相談内容を丁寧に聞き取り、必要な関係部署、機関につなげて相談者の支援を行っている。また、支援者向けのリソースマップの更新や、高校生、当事者等にも入ってもらい、若者の予防的な支援として、「15歳から18歳のための居場所支援マップ」を昨年度作成した。今年度は大学生にも入ってもらい、マップの更新や制度周知について、当事者である若者の意見を聞きながら検討していく。
〇小坂
今後も、例えば、地域の大学とゲートキーパー養成講座を共同開催するなどの連携、つながりをつくれる居場所の取組など、引き続き工夫を重ねての推進を。
(3)妊産婦について
〇小坂
厚労省の調査では、出産前後の女性の自殺が妊娠・出産に伴う精神的・社会的負荷と関連していることが指摘をされている。出産・育児期に心の不調を抱えながら支援につながれないケースがあることは社会全体の課題。安心して相談できる窓口、医療、保健、福祉が連携した支援体制の整備、周知啓発は喫緊の課題だと考える。妊産婦に対する現状の支援体制について伺う。
○ 子ども家庭部長
妊産婦への対応については、母子保健事業の一環として、ゆりかご・こくぶんじ面接、産婦新生児訪問において、産後鬱のリスクや育児不安の有無についてを確認するため、自己記入式のアンケートを実施している。これにより、産後鬱の可能性のある方や育児不安のある方に対しては、地区担当保健師などによって、電話の相談や戸別訪問を行っている。さらに昨年度から、特に支援が必要と思われる25歳以下の初産の方や、頼れる人が1人以下しかいない妊婦の方については、聞き取りを丁寧に行い、一人一人のニーズに応じた支援を行っている。
〇小坂
先日、多胎児を育てている方たちとお話をする機会があった。産前産後のリスクを抱えやすい多胎児家庭とは、妊娠期からしっかりとつながれる仕組みがあると大変心強いとおっしゃっていた。予防的観点からも、より一層丁寧な面接や訪問を求める。
(4)高齢者について
〇小坂
高齢の方に対しては、地域包括支援センターや医療機関と連携し、見守りや相談体制を強化することや、孤立を防止し、地域交流や生きがいづくりの場の提供、社会参加を促進する施策等が考えられるが、主な取組について伺う。
○ 福祉部長
第2次国分寺市地域福祉計画の自殺防止のための固有の支援として、高齢者とその家族、介護者が社会的に孤立することなく、生きがいを感じられる地域づくりを進めるため、相談体制の整備、認知症サポーター養成講座、地域生きがい交流事業等に取り組み、個別支援、地域づくりを進めている。
〇小坂
高齢者の社会的孤立を防ぐには、世代間交流の促進やICTの活用支援なども重要と考える。引き続き家族や介護者も含めた支援の充実を求める。
(5)生活困窮者について
〇小坂
先月の報道によれば、埼玉県内で食料支援団体を利用しているひとり親世帯の母親のおよそ半数にうつや不安障害の疑いがあること、このうち6割余りの人が重度の疑いであることが、明治大学公共政策大学院などが行った調査で判明。こうした家庭には食料支援だけではなく、メンタルケアや医療、就労などの複合的な支援を行っていくべきだとしている。生活苦は自殺の大きな要因の一つに挙げられる。生活困窮者への主な支援について伺う。
○ 福祉部長
こちらも第2次国分寺市地域福祉計画の自殺防止のための固有の支援として、生活困窮に陥った人に対する生きることの包括的な支援の強化、支援につながっていない人を早期に支援とつなぐための取組として生活困窮者の相談支援、貸付け事業等、重層的支援体制整備事業を通じた庁内関係機関等と連携して対応している。また、自立生活サポートセンターこくぶんじが生活上の困り事などを幅広く受け止め、本人に寄り添い、支援を進めている。
〇小坂
様々な支援につなげていく入り口としても、生活応援事業は非常に重要だと考える。取組と課題について伺う。
○ 福祉部長
社会福祉協議会のボランティア活動センターこくぶんじを中心に、食品の無料配布と暮らし、生活困窮に関する相談を毎月第3土曜日に開催している。食料品の調達については、社会福祉協議会が独自で購入するものと、未使用食品の拠点収集、防災備蓄食料品、地域から寄附された食料品を活用して行っている。現在の課題としては、物価高騰の影響によりお米の価格高騰と購入制限があるため、お米の調達が大変難しいと聞いている。また、先着50世帯のため、定員を超えた場合には別途自立生活サポートセンターこくぶんじで生活相談、食料品の配布を行っている。
〇小坂
物価高騰が続く中で、この事業を必要とされている世帯も増えているのではないか。状況については丁寧に共有し、必要な方に漏れなく支援が届くよう目を配ってほしい。今年もゲートキーパー養成講座に参加した。自殺予防対策は効果が目に見えにくく、実証も難しい中で、市の職員の方や市民に向けたこうしたゲートキーパー養成講座の継続的な開催は非常に重要だと考える。今回の様々な質問を通じて、本課題は全庁的な取組が必要であり、複合的な困難を抱える市民への丁寧な支援のためには、より一層の重層的支援体制の整備が不可欠だと痛感した。徳島県の自殺率が極めて低い町を調査した『生き心地の良い町』という書籍では、多様性を受け入れる雰囲気、悩みを隠さず相談できる風土、多角的な価値の尊重、プライバシーを守りつつ見守る文化、助け合いとやり直しが許される寛容さなどが自殺予防の要因として挙げられている。国分寺市においても「生き心地の良い町」を目指し、風通しのよいまちづくりを市民と共に考えていっていただきたい。