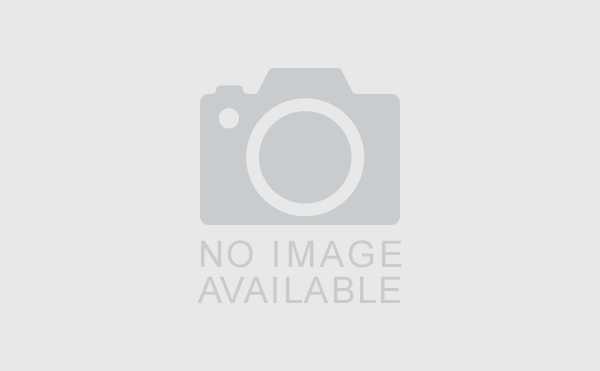小坂まさ代2025年第3回定例会一般質問3.図書館について
3、図書館について
〇小坂
図書館は、子どもから高齢者まで生涯にわたって学びや交流を支える地域の重要な知的インフラである。
(1)本多図書館市役所分館について
〇小坂
本年1月6日、泉町に新庁舎が開庁し、1階北側に本多図書館市役所分館もオープンした。親子で楽しめる絵本のコーナー、バリアフリー資料が並ぶりんごの棚、国分寺市ゆかりの絵本作家の作品、ガイドブックや地域資料、行政資料が並んでいる。1月の開館以降の貸出数等の実績、利用者の様子について伺う。
○ 教育部長
1月の開館から7月末までで貸出数2万4,726冊、リクエスト数は1万6,187冊。利用カードは、一般、児童合わせて393人が登録。以前の駅前分館と比較して多くの方が登録している状況。公園が目の前にあるロケーションであることから公園帰りに家族で立ち寄ったり、市民課の手続中に立ち寄る親子などが多く見受けられる。また、父親が子どもに読み聞かせをする姿などを見かけることもあり、市民にとって使いやすく、居心地のよい場所として利用されている状況。
〇小坂
私の方にも「図書館空白地区だった泉町に、土日も月曜も本を借りることのできる図書館ができて本当にありがたい」という声を何人もの方からいただいている。今後は、土日の閉庁時などに1階のスペースを生かしてのおはなし会やイベントの開催についても検討してほしい。
(2)旧庁舎用地に移設される恋ヶ窪図書館について
〇小坂
国分寺市の図書館の開館は、市役所分館を除けば、恋ヶ窪図書館は現在の場所からの移設ではありますが、実に40年ぶりにできる新しい建物でのオープンとなり、市民の期待が高まっている。本事業におけるこれまでの経過と今年度の状況について伺う。
○ 公共施設マネジメント担当部長
令和5年3月策定の国分寺市現庁舎用地利活用基本計画に基づき、令和5年度より複合公共施設の基本設計を実施。その過程においてはワークショップ等を開催。市民参加により、図書館内における「静」と「動」のゾーニング、入りやすいフリースペースの配置などについて、市民、利用者の皆さんから意見を収集、反映しているところ。今年度当初から民間事業者の公募を開始、11月に優先交渉権者を決定、公表していく予定。
〇小坂
複数回のワークショップやオープンハウスを行って、市民参加を通じて基本設計を取りまとめてきたことは承知している。この複合公共施設における運用の検討に際して、これからの市民参加の詳細について伺う。
○ 公共施設マネジメント担当部長
国分寺市旧庁舎用地利活用事業複合公共施設運用に関する基本的な考え方案を現在作成しており、10月からパブリック・コメントを実施する予定。この内容を前提に、本施設の供用開始に向けて引き続き市民意見を伺いながら検討を進めていきたい。
〇小坂
今後も市民の意見を聴く機会をぜひ設けていただきたい。奈良県葛城市では、地域の子どもたちや大人が共に使いやすくゆっくり時間が過ごせる場所をコンセプトに、身近なよりどころとなる施設づくりを目指し、基礎設計が終わった段階で市民座談会を複数回企画、新しい複合施設の概要を共有し、この施設でやってみたいこと、使い方の意見交換を目的として開催されたとのこと。小学生から大人まで幅広い世代が参加し、模型や動画、図面を見て意見交換を行った。市民の意見を反映させることで地域に根差した施設づくりが進められ、市民参加型のプロセスが施設の成功に寄与する重要な要素となっている。こうした事例も参考に、長く市民に愛される図書館となるため、子どもも含めた意見収集の機会をしっかりとつくってほしい。
(3)まちじゅうに図書館を
〇小坂
全国の自治体では、まちじゅう図書館、まちなか図書館、まちライブラリーという名称で、図書館を建物内にとどめず、まち全体に広げる取組が進んでいる。群馬県太田市の「おおたまちじゅう図書館」では、商店や事務所、個人宅に本棚を設置し、まちを歩きながら本と出会う場を提供している。長野県小布施町の「おぶせまちじゅう図書館」でも、町内のカフェや商店などに本棚を設置。国分寺市においても地域資源を活用したまちじゅう図書館のような取組を検討することで、まちのにぎわい創出や市民交流の促進が期待できるのではないかと考える。また、子どもたちにとって身近な場所で読書に親しむ機会が増え、読書習慣の定着にもつながるのではないか。子どもをはじめ市民全体の読書環境の充実と地域のにぎわい創出を両立させる、こうした方策について、市の見解を伺う。
○ 教育部長
現状として、子どもたちには公立図書館のほかに、小・中学校や学童保育所、保育所、児童館への団体貸出しや、リサイクル本や寄附図書などの図書館以外で活用できるものは、小学校の学級用、児童館、親子ひろば等にそれぞれのニーズに合った図書を提供している。一般の方々にはリサイクル市の開催など、本を手に取れる環境を提供している。また、市民による家庭文庫などもある。今後もこれまでの取組を引き続き行うとともに、本を手に取れる環境づくりに努めていく。群馬県太田市のまちじゅう図書館については、太田市美術館・図書館の設置目的である駅周辺のにぎわい創出のため、この施設を拠点とし、誰もが気軽に本との出会いを楽しめる環境を促進するために、新たな地域コミュニティの場として始められた取組と聞いている。この取り組みについて、もう少し調べさせてほしい。
〇小坂
太田市では、まちじゅう図書館に関わる方たちが集まる会も催されているとのこと。図書館の館内だけではなく、本と人に触れ合える場をつくることは、顔の見える関係づくりにも役立つと考える。まちづくりの観点から、また別の機会にも提案できればと思う。
(4)子育て支援策としてブックスタートの取組を。
〇小坂
NPO団体による2024年度の全国調査によれば、87.4%の自治体で、当該自治体に暮らす赤ちゃん全員を対象に絵本を贈呈する事業が実施されているとのこと。未実施自治体の20市町村が来年度以降に実施予定と回答、絵本のプレゼントのみも入れると、多摩26市では21市が既に導入済み。群馬県前橋市では、こんにちは赤ちゃん事業として保健師や助産師が各家庭を訪問。する際に絵本引換券を手渡し、また荒川区や八王子市では3~4か月健診の案内にブックスタート引換券を同封、図書館で絵本と交換できる仕組みを実施している自治体が多数ある。図書カードの作成、おはなし会や読み聞かせ講座の参加にこのような形でつなげている。これまでも本事業については一般質問を通して提案してきたところだが、こうした子育て部門との連携でブックスタート事業の検討を始めてみるのはどうか。
○ 教育部長
ブックスタートについては子育て関係部署と検討し、母子保健事業で実施しているファーストバースデーパスポート事業にて、どのような絵本がブックスタートにふさわしいか、それをまとめたブックリストを配布し、情報提供に努めている。今後さらに母子手帳交付時にブックリストを配布するなど、保護者の方が本の情報に触れる機会を拡大していきたいと考えいるが提案については、現時点で検討することは考えていない。他市、他自治体の情報収集に努めていきたい。
〇小坂
調査によるとブックスタートの所管部署は、図書館及び生涯学習課、社会教育課などが6割以上とのことだが、母子保健担当課及び子育て支援担当課が事業を担当している自治体も3割以上あった。親子ひろばだけではなく、図書館も親子で楽しめる公共施設として紹介でき、親子関係を育むツールとして絵本を使うこうした試みについて、子育て支援の視点からも必要であると考えるが見解を。
○ 子ども家庭部長
母子保健事業においては乳幼児親子と接する機会が多くあるが、全ての乳幼児親子と接する事業は、産婦・新生児訪問以外にはないような状況。こちらの事業では本の管理や配布が難しく、実施することは現状では厳しい。絵本を介して親子の愛情形成を促すことは大切な取組であると考えている。引き続き親子ひろばでの読み聞かせを行うとともに、ブックリストの配布などを図書館課とも連携して取り組んでいきたい。
〇小坂
ブックスタート赤ちゃん絵本は、3年に一度、専門家の方たちにより選書されている絵本。非営利支援価格で、通常の書籍流通とは異なるルートで出版社から直接NPOに提供され、自治体へ送られている。西東京市では絵本と子育て事業(ブックスタート)が平成15年度から始まり、図書館の案内とともに3~4か月児へ絵本とお薦め絵本のリストを配布し、読み聞かせの実演などを行っている。また、二十歳の集いとコラボした「この本よんだ?おぼえてる?」という企画を実施。会場では懐かしいという声とともに、「市が絵本をプレゼントしてくれていたことを初めて知った」「とても幼い頃から図書館と深いつながりがあったことをうれしく思った」という声が寄せられたとのこと。乳児からの読み聞かせは、後の子どもの読書活動に大きな影響を与える。読み聞かせに関心の薄い方に対しても、赤ちゃんと一緒に図書館へ足を運ぶきっかけをつくることができるこの試みについて検討を要望する。
(5)子ども読書手帳について
〇小坂
子ども読書活動推進計画の中で触れられている読書手帳を今年度より作成し、配布していくとのこと。どのようなものか。
○ 教育部長
子ども読書手帳は、第四次国分寺市子ども読書活動推進計画に位置づけている事業で、子どもの読書習慣の定着は乳幼児から小学校低学年までの時期を重要と考え、まずは家庭における読書環境づくりに取り組むこととしており、保護者が乳幼児に対して読み聞かせした本の題名や、そのときの子どもの様子や本の感想などを記録できるものと想定している。手帳を活用することで子どもの成長や思い出を振り返ることができ、成長した際の親子のコミュニケーションが期待できると考えている。今年度中に作成し、配布する予定。次年度以降も継続して取り組むことが効果的であると思っている。
〇小坂
読書を通じて新しい世界の扉を開く喜びを子どもたちに伝えるツールとして、単に配布するだけではなく、手帳の使い方も含めた絵本紹介イベントなども期待している。
(6)図書館ボランティアについて
〇小坂
図書館では、本棚の整理等のボランティアの受入れを行っているが、市民が図書館とつながる有益な取組と考える。ここ数年の活動人数と周知方法について伺う。
○ 教育部長
参加人数は、令和4年度は39名、令和5年度も39名、令和6年度は64名。周知については市報、ホームページ、図書館だより、施設の館内掲示にて図っている。
〇小坂
令和6年度は大変増えていることを心強く思う。令和2年5月より中学生も参加できるようになった。図書館ボランティアの活動のほか、中学校との連携について伺う。
○ 教育部長
図書館ボランティアは中学生以上を対象としており、通常の図書館ボランティアのほか、中学生のサマーボランティアを受け入れている。図書館ボランティアは、図書館を通じて地域で活躍する場を提供し、人との結びつきを強めるということを目的としているが、サマーボランティアについては、図書館の仕事を知ってもらい、社会への理解を深め、地域を支える一員として成長していくことを目的としている。サマーボランティアの活動は、第二中学校の協力により、夏休み期間中の数日間、書架整理等を行っている。また、通常のボランティア活動として書架整理や、リサイクル市や、市のイベントにスタッフとして活動してもらっている。また、中学生の職場体験から図書館ボランティアにつながる事例もある。中学校の図書委員会活動との連携については、図書館福袋の本の選定や図書委員作成のポップの展示、ヤングアダルトのお勧め本リストの作成など、活動を広げている。
〇小坂
図書館は近年、家庭や職場に次ぐサードプレイスとして、誰もが自由にくつろげる居場所としての役割が注目されているが、さらに単なる居場所を超えて学び、創造し、挑戦できる場としての重要性が増している。サードプレイスの先の第4の場所、フォースプレイスとして、図書館が市民を情報の受け手にとどめず、主体的に学び、創造し、未来に向けて挑戦する拠点としてコミュニティや地域社会における多様なニーズに応え、次世代の知的・文化的活動の中心となっていくことが期待されている。これからも利用者懇談会などに寄せられた声を大切にしながら、より使いやすい図書館運営を要望する